グローバル
キャリア
事業所長

カルビーポテトで活躍する社員の歩みには、挑戦と成長のドラマがあります。
初めての挫折を乗り越えた瞬間、新しい部署で掴んだ手ごたえ。
そんな一人ひとりのストーリーを通して、未来を切り拓くヒントをお届けします。

北海道馬鈴薯事業部 事業所長
北海道の斜里に配属となり、契約生産者と協働しながら品質・収量向上プロジェクトを推進。契約生産者と信頼関係を築きながら栽培アドバイス、収量データ分析、現場巡回での課題抽出を行う。
支所長に抜擢され、フィールドマン業務に軸をおきながらも支所運営、マネジメントなど統括業務を担当。年間スケジュール策定、収穫期の受け入れ調整、チームマネジメントを行う。
全国の貯蔵環境や品質をモニタリングを行い、貯蔵条件の改善提案、出荷順序の最適化、トラブル時の現地支援を担当する。
米国輸入じゃがいも品質改善プロジェクトに社内公募で参加。現地で栽培から貯蔵、出荷までの工程調査とデータ分析を実施し、原因特定後に改善策を契約生産者・協力会社と協議・実行。プロジェクト後は輸送契約交渉や納期・品質調整を担当する。
馬鈴薯事業所長として7支所の統括担当。支所長の育成、組織戦略立案、人員配置、予算管理などを行い、全社目標達成に向けて事業運営とマネジメントを行う。
未知の領域に飛び込むこと。
これが私にとって、キャリアを築くうえでの最大のエネルギーとなってきました。
大学では水産学部を卒業し、農業という新しい業界に飛び込んだ私にとって、入社1年目はまさにゼロからのスタートとなりました。知識も経験もない中で、先輩方のOJT指導をうけながら栽培に関するノウハウや契約生産者さんとの関係の築き方などひとつずつ学んでいきました。
経験を重ねていき支所長に就任した初年度には、じゃがいもの収量不足という思いがけない事態に直面することもありました。追加のハーベスターを手配し、自ら収穫の応援にも入りながら個々のメンバーに指示を出し、チームをまとめながら乗り越えることができました。この経験を通して、プレーヤーからマネジメントへ意識を転換する転機を迎えたように感じます。

貯蔵技術支援課で貯蔵庫の品質チェックや改善提案に取り組んでいた私に、「アメリカでの輸入じゃがいもの品質改善プロジェクト」の話が舞い込んできました。このプロジェクトでは、アメリカ現地に赴き、栽培から貯蔵、出荷までの各工程を確認し、品質改善に取り組むことが求められました。現地調査や契約生産者との直接交渉という新しいフィールドに、期待とともに少しの不安も感じていましたが、それでも、これまでの経験を活かして「挑戦してみよう」という気持ちが勝り、一歩を踏み出す決意を固め公募に手を挙げました。
アメリカ現地では、栽培から貯蔵、出荷までの各工程を一つずつ確認し、問題の原因を丁寧に探りました。言葉や文化の違い、左ハンドルの運転に戸惑いながらも、現地契約生産者や現地の協力企業とじっくり対話を重ね、課題に一つひとつ向き合うことで改善に結びつけることができました。周囲の支えのおかげで、多くの壁を乗り越えることができ、品質改善という大きな成果に繋がりました。このプロジェクトを通じて、課題設定から改善実行まで一貫して取り組む力を養うことができ、社内外のメンバーと協力しながら目標を達成するという自信も得ることができました。

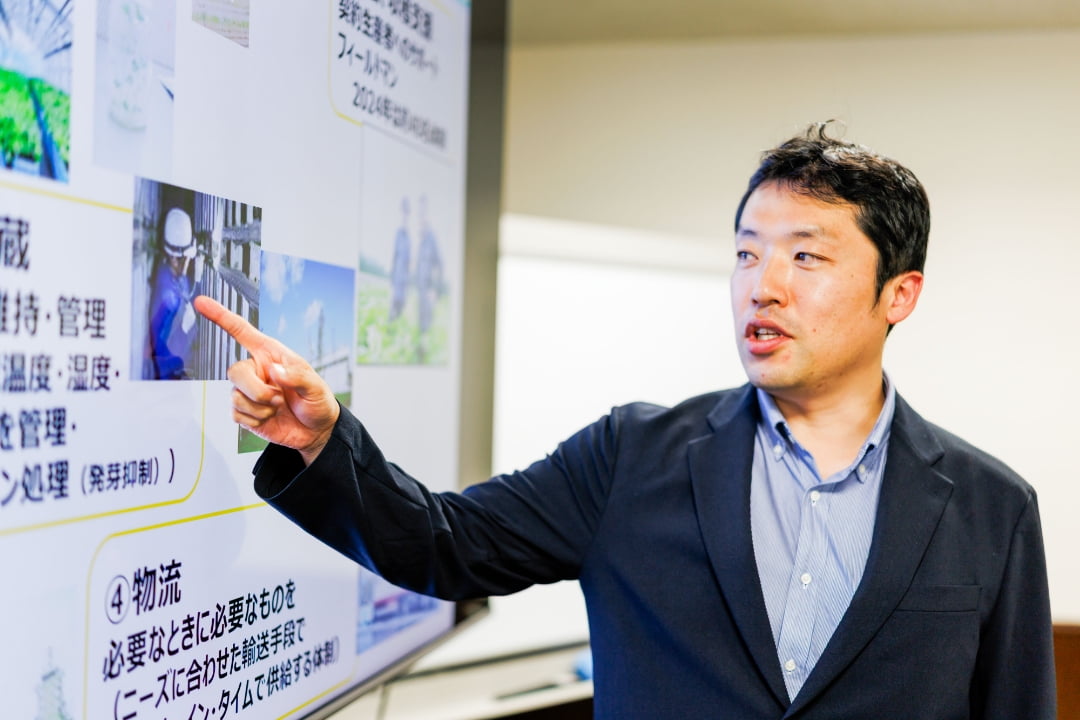
帰国後は2年間の海外出向を経験し、サプライヤーとの契約交渉や船会社との調整、品質・数量・納期の管理など、輸入に関わる実務を幅広く担当しました。調達先との交渉や納期調整など、国際業務の実務を通じてグローバルな視野と課題解決力を大きく伸ばすことができたと思います。グローバル調達のノウハウを深めると同時に、多くの取引先と良好な信頼関係を作れたことや多角的な視点を得る経験ができたことは、私自身大きく成長することができた2年だったと思います。
現在は馬鈴薯事業所長として、現場で培った実行力、マネジメントの視点、そして調達の経験を活かし、チーム一丸となって事業を推進しています。次に目指すのは、新規事業やDXといった新しい分野でのチャレンジ。これからも“未知”を楽しみ、仲間の力を借りながら、一歩ずつ前に進んでいきたいと考えています。


業務標準推進課 主任
入社1年目は北海道でフィールドマンとして契約生産者の栽培支援と貯蔵管理を担当。農業知識ゼロの状態から、「声を聞く」姿勢で一人ひとりの悩みや栽培状況を丁寧にヒアリングし、信頼関係を築きながら知識を習得する。
支所の異動を経験しながら植付けから収穫までの全行程を2サイクル経験し、栽培技術や品種、天候に関する知識も深めていく。農協や運送会社など取引先との折衝も行い、交渉力や調整力も身に着ける。
フィールドマンとしての経験を活かして、業務手順の整備や研修企画、仕組みづくり支援を担当している。「標準化」「教育」「効率化」を三本柱に関係部署と協働しながら改善策を立案し、組織全体の生産性向上や業務の見える化に貢献している。
入社後新入社員研修を経てフィールドマンとして北海道の支所に配属になりました。約50名の契約生産者を担当し、栽培支援から貯蔵管理まで一貫して経験を積むことができました。じゃがいもに関する知識はゼロからのスタートで、契約生産者さんの顔と名前を覚えることに少し時間はかかりましたが、コミュニケーションを重ねながら、専門的な栽培技術を習得していき、契約生産者さんとより深い信頼関係を築くことができたと思います。2年目には春の植付けから秋の収穫までの圃場の一連の工程を経験し知識を増やしたことで、契約生産者さんへの支援に自信を持てるようになりました。また、日々フィールドマンとして経験とスキルを増やしていく中で、業務課題や改善点が見えてきた時期でもあったように思います。
その後、上司との面談の際に「現場を支える間接部門に携わりたい」という想いを伝えたことがきっかけで、上司からの後押しもあり業務標準推進課へ異動することとなりました。この部署では、フィールドで培った知識や経験を活かしながら、さまざまな業務の「標準化」「教育」「効率化」を三本柱に、業務プロセスや作業手順の統一を図ること、ばらつきが無いスキルや教育、マニュアル整備やDX推進による業務の効率化を行なっています。自分が感じていた業務の課題を解決し、フィールドマンや現場を支える立場へとキャリアの舵を切ったのが、大きな転機となりました。


フィールドマン時代に『もっと効率よくできないか』『ここに課題があるのでは』と感じた自身の経験が、業務標準推進課での取り組みの原点でした。
貯蔵管理基準や品質検査基準の見直しを行い、基準が作成された背景を十分に理解した上で、現状に即した基準や運用へと改善しました。この際、現場の意見を反映し運用の柔軟性を確保することにも注力しました。これらの変更について関係者への周知を徹底し、人による作業のばらつきを減少させることで、品質向上に貢献できたことを実感しております。
また、過去の数値データ管理についても、Excelで年度ごとの管理から、データベース化ツールに移行して一元管理を行いました。このことにより『データの保管場所が分からない』『過去実績を比較しづらい』という使いづらさを解消し、誰でもワンクリックで必要なデータを確認できるようにしたことで効率化を進めることができました。

しかし新しい仕組みや管理方法を導入して終わりではなく、仕組みの定着化には導入後に現場の細かな声を丁寧に聞き取ることが重要です。実際に使っている人の作業効率が上がっているか、使いづらい箇所は無いかを確認していきます。定期的なヒアリングやワークショップを実施し、『現場の声が反映されている』と思ってもらうことで現場と信頼を築きながら調整を重ねています。
これらすべては、フィールドマンとして日々に感じた“現場での気づき”を起点にした改善だからこそ実現できたもので、経験が活かされていると実感します。今後はAIによる収量予測にも挑戦し、北海道の農業現場を次のステージへ導いていけるような取り組みを進めていきたいと思っています。

外部リンクに遷移します。